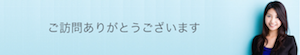生理休暇と法律について解説

生理休暇とは
働く女性にとって、生理は非常につらいものですが、そんなときに取得できる休暇に、生理休暇があります。
以前は、月経痛のことで職場に相談しにくい空気があり、女性が生理による体調不調を感じても、職場に相談できない、恥ずかしいという人が多数でした。
そして、月経痛は「我慢するもの」という意識があるせいで、生理休暇を取得しにくいのが実際でした。
しかし、近年は働く女性への理解が深まる中、生理休暇を取得する女性社員がだんだんと多くなってきています。
ここでは、生理休暇についての法律的な知識をまとめてみます。
法律
生理により就業が 困難な職員から請求があった場合に与えなければならない休暇です。
根拠となる労働基準法第 68 条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定されています。
自動的にもらえる休暇ではありませんので、請求しないときに生理休暇がもらえなくても、違法にはなりません。
日数
生理の経過は人によって異なるため、生理休暇の日数を限定することはできません。
なお、一般的な会社では、日単位、半日単位、または時間単位で請求できるように運用しています。
診断書
生理休暇を取得するにあたり、証明を要求される場合がありますが、その場合、医師の診断書のように厳格な証明は、法律上は、必要ありません。
同僚の証言など、簡単なものでよいとされています。
生理中の女性をわざわざ診療所に出向かせることは、女性に負担をかけることになり、生理休暇の取得の意味が無くなるからです。
給料
生理休暇を有給とするか無給とするかは、労働基準法では特に規定されていません。
したがって、生理休暇を有給とするか無給とするかは、会社ごとに、就業規則で定めることになります。
生理休暇を有給としている場合に、その有給の日数を限定することは、それ以上の休暇が与えられ ることが明らかにされていれば差し支えありません。
関連法令(労基法第68条)